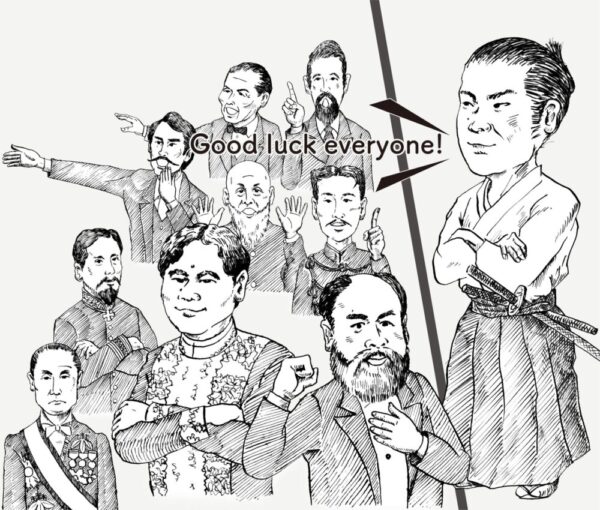
4-4.
県域の拡大
慶応4年(1868)の兵庫県設置時の県域は摂津・播磨の幕府領・旗本領をあわせたものであり、現在の県域の大半を占める大名領はまだ藩のままでした。明治2年(1869)の版籍奉還により土地・人民は朝廷に返上されますが、藩は 存続し引き続き藩主が知藩事として統治していました。明治 4 年(1871)7 月、廃藩置県がおこなわれ、藩がそのまま県となり、現在の兵庫県域には 30 を超える県が成立することになりました。しかし、11 月には行政区画の全面改正がわおこなわれ、現在の兵庫県域は、兵庫、飾磨(播磨全域)、豊岡(但馬全域、丹後全域、丹波 3 郡)、 名東(阿波、讃岐および淡路全域)の 4 県に編成されます。明治 9 年(1876)8 月、第七代神田孝平知事の時、飾磨県と豊岡・名東両県の一部が兵庫県に編入されて、ほぼ現在の県域が確定しました。このような大きな県域になった理由については、開港場である兵庫県の力を充実させるために飾磨県と豊岡県をひとつにしたと言われています。


 選択画面に戻る
選択画面に戻る
